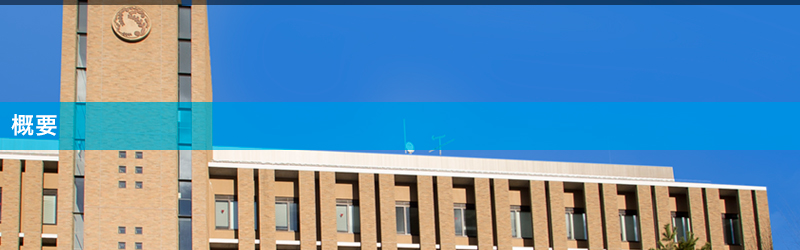
ごあいさつ
「公」を真剣に議論できる学び舎

伏見 岳人
東北大学公共政策大学院は、昨年の2024年に、20周年を迎えました。2004年に、公共政策分野における高度専門職業人の養成を目的として、本大学院が発足してから、すでに20年もの時が経ったのです。その間に修了した多くの人々が、さまざまな公共政策の現場で日々活躍しています。
公共政策の現場で働くためには、どのような資質が求められるでしょうか。
まず、「公」とは何か、を根源的に考える能力が、全ての基礎になります。「公」のあり方は、時代によって変化し、これからも変わり続けます。それに伴って、「公」に対する社会的ニーズも、今日では非常に多様化しています。それらを的確に把握しつつ、より良い「公」の実現を目指して、共同体の一員としての役割を果たす心構えを、公共政策に従事する者は必ず備えていなければなりません。
その能力と姿勢を、具体的に鍛える場所こそが、ここ東北大学公共政策大学院です。
本大学院の最大の特徴は、「公共政策ワークショップ」に代表される体験型授業プログラムです。公共政策の現場で長年奮闘してきた実務家教員と、法学・政治学の最先端の研究に挑戦している研究者教員、それに多様なバックグラウンドを有する学生たちが協働して、現在進行形の政策課題に実践的に取り組んでいます。
たとえば、2024年度には、コロナ禍で傷ついた観光政策をポスト・コロナ時代にどうすればよいか、出生率低下が進む日本の家族政策はどうあるべきなのか、東南アジアなどの海外に拠点を有する特殊詐欺の問題にいかに対処すべきか、2011年の東日本大震災で原子力災害に見舞われた福島沿岸部の復興まちづくりをどのように進めるべきか、といったテーマが扱われました。
いずれも、我々の未来を占う重要な政策課題ばかりであり、そして簡単には答えの出ない難問ぞろいです。あらかじめ模範解答の載っている教科書や解説書は、全く存在していません。しかし、その解決策を探し求めるべく、一年間、さまざまな現場で働く人たちにインタビューを重ね、数多くの文献や資料を読み解き、時には夜遅くまで仲間たちと議論を重ね、どのチームも独自性のある解決策を提言するまでに至りました。
また、本大学院では、法学や政治学、経済学の専門知識を教える多彩な授業が実施され、政策分野に関する演習も数多く展開されています。それらを通じて、公共政策の企画立案に求められる専門性を養いつつ、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を錬成することを目標としています。
2024年9月に開催された「東北大学公共政策大学院20周年の集い」には、全国各地から、多くの修了生や元教員が駆けつけてくれました。そこで交わされた会話は、やはり「公」のあり方について、それぞれの公共政策の現場に引きつけて考えるものばかりでした。かつて本大学院において、「公」の未来について、真剣に議論した共通の経験は、どれだけ時を経ても色あせない大切な基礎力になっているようです。
本大学院の門をたたき、新たな伝統を共に作り上げてくれる皆様との出会いを、心よりお待ちしています。

