Ⅰ.前期
2024年4月9日、WSDは主担当の御手洗教授による東日本大震災の福島県における被害や現在に至るまでの道のりについての講義から始まりました。同日には、学内の大熊町出身の学生の講話を伺い、研究対象である福島県の原子力災害被災地に関するインプットを行いました。
また、4月23日には福島県双葉郡双葉町へ訪問し、5月にはメインフィールドである南相馬市小高区で合宿を行いました。門馬市長や市役所職員の方、住民の方々から地域の現状や課題を詳細に伺い、課題を自分事化するきっかけになりました。
前期では講義や文献の輪読に加え、現地の方へのヒアリングを数多く行い、各メンバーが課題を特定するとともに、困りごとの自分化に取り組みました。また、小高の復興について考えていくにあたり、大目標の議論を丹念に行い、「選ばれる小高づくり」としました。
そして中間報告会へ向けた大まかな課題感や提言の方向性をまとめていきました。

双葉屋旅館

市内の製造企業への視察(ドローン制作)
Ⅱ.中間報告会
7月15日から16日に行われた中間報告会では、前期の活動内容に加え、特定した課題についてスライドにまとめ発表しました。
中間報告会に向けて、WSDでは「復興とは何か」という問いにはじまり、「なぜ復興まちづくりに取り組むのか」や「なぜ南相馬市小高区で取組むのか」といった内容を話し合いました。また、WSDは施策分野を「ひと・くらし・しごと」に分類した上で、その意義や大目標との関係についても確認しました。スライドでは、スライド担当がデザインや体裁を丹念に点検し、見やすさやデザイン性にも配慮してスライド作成に取り組みました。

中間報告会リハーサルの様子
直前の休日には、リハーサルを行い、質疑対応などの練習を繰り返しました。
当日は、多くの鋭い質疑をいただきましたが、一つの質問に対して複数のメンバーが補足するなど「フリーライダー禁止」というWSDの信条を体現しました。
Ⅲ.夏期休業
夏季休み中の8月19日~21日には、WSD恒例の夏合宿が行われました。前期に取り組んだ課題の特定をさらにブラッシュアップするとともに、他分野にも課題がないかを探りました。学生が主体となってヒアリングを企画し、事前質問の作成やアポ取りを行いました。3日間という短い期間でしたが、かなりハードな合宿となりました。
加えて、WSDが支援をいただいているF-REI(福島国際研究機構)を訪問し、研究について講義をいただいただけでなく、WSDの研究について重要なフィールドバックをいただきました。

F-REIでの発表の様子
また、福島第一原子力発電所や中間貯蔵施設を視察させていただき、原発被災地の実情をより深く理解することができました。なおWSDの夏合宿での取り組みは、全国紙で報道されました。

福島第一原発での視察
Ⅳ.後期
後期には、前期及び夏合宿で特定した課題に対して、有効な施策案を構築すべく、文献調査及びヒアリング調査を中心に行いました。
11月には、北海道大樹町や上士幌町を視察し、宇宙産業に取り組む自治体やマルシェを運営する企業にヒアリングを行いました。
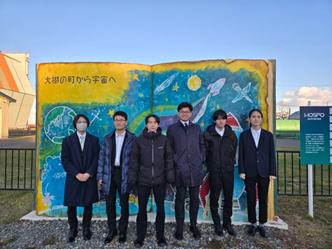
大樹町での視察の様子

上士幌町へのヒアリングの様子
Ⅴ.最終報告会
2024年12月16日から17日にかけて、WSDの一年間の活動と提言の発表を行う、最終報告会が行われました。最終報告会に向けて、WSD全体で再び「復興とは何か」「復興まちづくりとはどのようなものか」といった復興観を議論しました。さらに、4月から意識してきた、個別の施策の寄せ集めにせずに「グループ」での提言となるようにシナジー案なども検討しました。報告会前には、M2のチューターの方だけではなく、南相馬市役所の職員などにもお越しいただき、フィールドバックをいただきました。
発表当日は、中間報告会同様に一つの質問に対して複数のメンバーが回答するというWSDらしさを発揮しました。また、コメンテーターとして門馬和夫市長にもお越しいただき、「発表内容の完成度の高さに驚いた。こういったやり取り一つ一つが復興に大切。住民にとって幸せなことだと思う」とお言葉をいただきました。

最終報告会での質疑対応の様子

発表後の市長との交流の様子
Ⅵ.現地報告会
年末年始にかけては、「最終報告書」の執筆に取り組み、約200頁をメンバーが共同で書き上げました。
2月4日には、研究フィールドである南相馬市小高区(浮舟文化会館)で、市長及び市役所職員、住民などにお越しいただき、一年間の報告会を行いました。発表後には、質疑の時間を設け、住民の方との意見交換を行うなど非常に貴重な時間になりました。多くの住民の方と一度に交流する機会は限られていたため、より詳細な小高の課題について理解を深めることができました。
同日には原町高校に伺い、市内の高校生に公共政策大学院の取組や、高校生の授業で行われている「探究学習」にも通じる、課題設定や研究方法での重要なポイントについて説明させていただきました。また、後半にはグループに分かれ、大学生活などについて懇談しました。
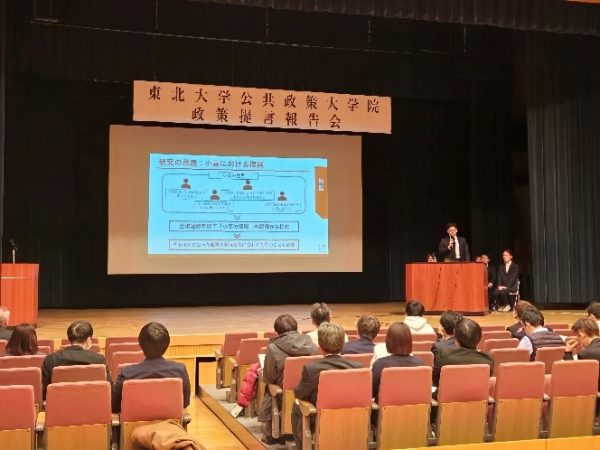
現地報告会での発表の様子

職員の方との記念撮影

報告書の手交の様子


原町高校での発表の様子
また、3月8日には仙台国際センター(仙台市)で、「世界防災フォーラム2025(WBF)」が開催され、WSDのメンバーが一年の活動を報告しました。


WBFでの発表の様子
Ⅶ.おわりに
最後になりますが、一年間の活動では、メンバー全員が南相馬市及び小高区の課題を「自分事」として捉え、何とかして貢献したいという熱い気持ちで取組んできました。一方、政策を検討するにあたっては、冷静に考える姿勢を学んできました。一年という限られた時間でしたが、これまで以上に南相馬市小高区への思い入れが強まりました。今後の各メンバーの経験においても、市長、職員、住民の方々の思いとともに歩んでいきたいと思います。
1年間、WSDの研究活動に際して大変お世話になりました関係者の方々に、厚く御礼申し上げます。

